健康寿命とは何か 最新データをまとめてます!
目次
▼健康寿命 厚生労働省の定義を簡単に説明
健康寿命という言葉があります。これは、平均寿命とは違います。
厚生労働省の定義は次の通りです。
「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」
となっています。
平均寿命との違いは、日常生活に制限がある「健康でない期間」が含まれていないことです。
つまり、日常生活を送る上で誰かの手によって介護や看護などの世話にならず、趣味や生きがいを持ちながら、自立して健康な生活ができる期間と言えます。
近年PPK(ピンピンコロリ)という言葉が盛んに使われ始めました。これは、元気に過ごして亡くなる時はコロッと逝こうという意味ですが、実現するのは簡単ではありません。
厚生労働省の健康寿命 最新発表2019-2020年では
公表した最新データは厚生労働省が2018年3月に発表した2016年のものです。
2019健康寿命都道府県別トップ3 まだ2016年のもの
| 男性 | 女性 | ||||
| 順位 | 都道府県 | 健康寿命 | 順位 | 都道府県 | 健康寿命 |
| 1 | 山梨 | 73.21 | 1 | 愛知 | 76.32 |
| 2 | 埼玉 | 73.10 | 2 | 三重 | 76.30 |
| 3 | 愛知 | 73.06 | 3 | 山梨 | 76.22 |
男性・女性とも愛知、山梨が上位を占めてます。その県・地域でよく食べるものの違いとかあるのかもしれませんね!
テレビのケンミンショーで地域特有の食べ物を紹介してくれるのでチェックしてみてください。
健康寿命は全都道府県のものがあるので、その土地で違うというデータはおもしろいし、興味がわきますね!自分の住んでいる地域はどうなっているのでしょうか??こちら↓↓に健康寿命を延ばすにはどうすればよいか忘れがちな3つの方法もまとめてます。
*健康寿命ランキング2018-2017-2016最新【ベスト-ワースト5を延ばすには!
健康寿命と平均寿命 厚生労働省発表は2019-2020全国平均は 2016年のもの
・2018年発表の2016年の全国平均健康寿命
男性の平均寿命が80.98歳に対し健康寿命は72.14歳、女性の平均寿命が87.14歳に対し健康寿命は74.79歳
・平成25年(2015)に2年前の平成23年(2013年)のものでは、
男性の平均寿命が80.21歳に対し健康寿命は71.19歳、女性の平均寿命が86.61歳に対し健康寿命は74.21歳です。
次の公的な発表は2017年の年末から2018年初めになるということで、2年おきにいつも厚労省から発表があります。
なので次の健康寿命のデータは2015年のものが2017年末ほどに公開されるということになりますね。
→実際には2018年3月でしたね(;’∀’) 訂正で2年から3年おきに発表されることになりますね。
次は2020年3月あたりに2018年のものが厚生労働省から発表されることになると思います。

このように平均寿命と健康寿命の差が開いているという事は、平均寿命が延びても不健康で介護が必要な期間も延びていえるという事です。
それらは家族介護による心身の負担だけでなく、経済的負担も招きます。個人だけの問題にとどまらず、医療費や介護費用の増加は日本社会の深刻なものとなっています。
今後さらに日本は少子高齢化が進むといわれています。若者だけで高齢者を支えることはますます困難となっていきます。
一人ひとりが自立して幸せな人生を長く過ごすことは、健康寿命を延ばし日本社会を支えるために大切なことと言えるでしょう。
▼健康寿命の計算方法はサリバン(sullivan)法を使う
平均寿命とは違う健康寿命はどのような方法で求めるのでしょうか。
計算にはサリバン法というものを使用します
そして、国民生活基礎調査の二つのデータをもとに算出されます。
国民生活基礎調査とは厚生労働省が昭和61年から実施している調査です。保健、医療、福祉、年金、所得など国民生活な基礎的事項について調査します。
対象となる世帯やその調査数は、無作為に抽出された地区の世帯を対象としており、サンプリング数は毎回の調査内容によって違います。対象の世帯には事前に調査票が配布されますので、回答したことがある方もいるのではないでしょうか。
以下は平成24年「健康寿命における将来予測と背勝習慣病対策の費用効果に関する研究班」のまとめたものを参照、引用しています。
A:国民生活基礎調査の中に「あなたは現在健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。」という質問があります。
この問いに対し、「ない」と答えた回答を日常生活に制限がないと定め、性別、年齢階級別の日常生活に制限のない者の割合を求めます。
次に生命表から定常人口と生存数を得ます。性別、年齢階級ごとに、定常人口に日常生活に制限のない者の割合いを乗じる(かける)ことにより、日常生活に制限のないものの定常人口を求めます。
次いでその年齢階級の合計数を生存数で割ることにより「日常生活に制限のない期間」を求めることができます。
生命表とは、年齢別、男女別などに分類し、生存数、死亡数および生存率、死亡率、平均寿命などが乗っている表の事です。
定常人口とはx歳(ある年齢)からx+n歳に達するまでの延べ生存数を足したものです。
B:「自分が健康であると自覚している期間の平均」も国民生活基礎調査と生命表を基礎情報とし、同じくサリバン法を用いて計算します。
「あなたの現在の健康状態はいかがですか」という質問に対し、「よい」「まあよい」あるいは「ふつう」と回答した数を自分は健康であるという人の数と定めます。その割合を用いて、上記と同じ方法で求めます。
AとBのどちらのデータを用いるかは国や各都道府県や市町村ででも違います。
Aについては客観的で自己申告したものであり、Bでは主観的で自己申告したものとなっています。
いずれも健康な人の平均寿命を求めているという感じになっています。
無作為抽出であり、どこまで実情にあっているのか疑問に思う点もありましたが、平均寿命と比較することで問題点を明確にすることができると思いました。
△平均寿命や健康寿命との差をみる厚生労働省発表データはこちらから↓↓
≫平均寿命2017健康寿命世界ランキング都道府県別ベスト-ワースト5【1位〇〇県
まとめ
健康で長生きをするということは誰もが願っていることでしょう。
長寿国となった日本にとって健康寿命をいかに延ばすかが課題となってきます。
今から、老後について考え趣味や生きがいを持ちながら自立して生活できるように、意識していくことが大切ではないでしょうか。



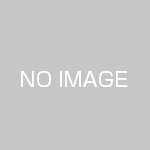
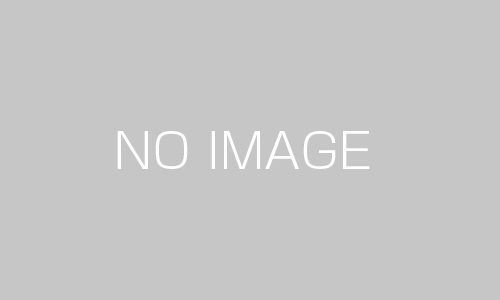


この記事へのコメントはありません。